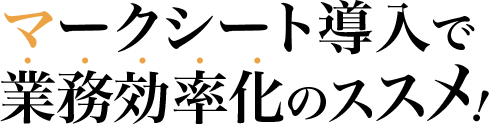公開日:
|更新日:
マークシート導入する前に知りたい質問や知識
学校の試験や企業のストレスチェックなどに使われるマークシート。
しかし導入を検討する際には知っておきたい知識が多いのは確か。
ここではマークシート導入するときに確認しておきたい知識を導入事例やQ&Aを交えて詳しくご紹介します!
マークシートの導入目的や事例について紹介します!
マークシートと聞くと、まず思い浮かぶのはテストや試験。
しかし、マークシートの活用は他にも多くあります。
採点や集計
メジャーな導入目的として、採点や集計に使うことがあります。
これは、採点や集計時間の短縮を主な目的としていて、テスト結果の分析まで。
さらに採点ミスの減少や、フィードバックの効率化など、採点スタッフの人件費削減にもつながっています。
アンケート
マークシートをアンケートに利用する事例もあります。
学校の卒業生アンケートや従業員の満足度調査など幅広く使われています。
これによって、課題に抽出やデータ管理に簡略化・アンケート用紙作成のコスト削減などができるようになります。
個人情報の管理
社員に勤怠管理や学生の進路調査・出欠確認などに利用する事例も。
定期的に情報収集を行う必要がある場合にミスなく一括管理が可能になり、転記ミスや代理出席の防止にも役立てています。
病院やストレスチェック
病院やストレスチェックにも活用されています。
健康診断の問診票やストレスチェック・病気の研究調査まで使われている事例も。
さらに、患者の満足度調査や、医療スタッフの適性検査にまで導入実績があります。
このように、マークシートを導入し様々なシーンで活用することでデータ管理の簡略化や人件費の削減など大きな効果をもたらすことが可能なのです。
マークシートを導入する前に知っておきたいこと4つ
OMRとは?
OMRとは、Optical Mark Reader(光化学式マーク読み取り装置)の頭文字で、マークの読み取りに特化した機械。
マークシートに記入されたマークを読み取り、パソコンへ瞬時にデータ転送できます。
認識が非常に優れており、光センサがマークの有無を直接認識するのでゴミなどによる誤認識はほとんどありません。
そういった理由から、国家試験などのミスが許されない場面ではOMRが使用されることが多いのです。
しかし、認識できるのはマークのみで、記述された文章や単語は認識できないことも特徴となっています。
OMRとスキャナの大きな違いとは?
まず、OMRとスキャナの違いは、精度・スピード・コストの3つ。
精度に関しては、OMRの場合、処理中も静電気の発生が少ないので、ゴミの付着を極力防ぐことができます。
さらに、消し残しを塗られたマークとして誤認識するといったことはありません。
一方、スキャナは、印刷時のゴミをマークとして認識してしまうこともあり、消し残しをマークとして誤認識してしまうことも。
紙詰まりなどによる読み取り画像が変形してしまうといったこともあります。
処理スピードはOMRが非常に優れており、マークシート用紙の処理は最速クラスといわれています。
ただし、コスト面から比較すると、OMRは高額なものになると100万円以上するものも。
コスト面では導入時のハードルが高くなってしまいます。
スキャナはORMと比べると精度や速さは劣ってしまいますが、学校のテストやアンケート・ストレスチェックなどに気軽に使え、他にも運用できます。
このように、マークシートの読み込みにおける精度や速さといった点では、OMR、導入コストの面ではスキャナがおすすめです。
マークシートを導入するときに気にしたい会社選びのコツ
マークシートの実施を検討する際、どのような会社を選ぶかは目的と費用によって基準が様々。
例えば、万単位の膨大な調査対象がある場合は、導入や用紙作成・集計作業まで任せることができる会社がいいかもしれません。
ただやはりそういった場合はどうしてもコストが高くなってしまいます。
一方、なるべく低コストでマークシートの導入をしたい場合は、自社にあるOA機器を使ってマークシートの導入ができる会社を検討してもいいかもしれません。
ただし、前述のように、スキャナなどの利用になってくるため、一定の水準の読み取りができればいいといった場合にはおすすめです。
必要な機器は?
まず必要な機器はマークシート用紙・スキャナやOMRなどの読み取り機器・読み取りソフトの3つ。
こちらをひとつずつ解説していきます。
マークシート用紙
使用するマークシートは、もともとある商品から最適なものを選ぶか、カスタマイズしたオリジナルのものを発注する。
もしくは、普段使っている用紙に印刷するかの3パターンです。
ただし、OMRを使用する場合は、専用の用紙を使わなくてはいけないため、普段使っている用紙を利用できません。
スキャナの場合、精度は落ちますが、どのパターンにも対応できます。
読み取り機器
マークシートの読み取りには、専用機器であるOMR・スキャナや複合機を使用する方法があります。
OMRは専用のマークシート用紙を使う必要があり、そのぶんコストは高めです。
一方、自社にあるスキャナや複合機を使う場合は、ソフトとの相性が適切かどうかも重要です。
適切なソフトを選べれば既存機器の利用ができるのでコストを抑えることができます。
ソフト
OMRやスキャナはマークシートを単体で読み込むことができず、ソフトウェアが必要になります。
ただし、通常の場合はOMR・スキャナ・マークシート用紙の購入時に付属品として購入可能。
つまり、ソフトのみを他で探す必要はないのですが、取り扱う会社によって精度や信頼性は様々。
セキュリティもしっかり考える必要があるので、導入先の実績や口コミをよくチェックしましょう。
ここからはマークシート用紙や機器などの気になることを質問形式で確認していきます。
マークシート用紙はどうやって作っていますか?
マークシート用紙は、様々なカスタマイズが可能で、水準の高い制作技術スタッフが描画ソフトなどを使用して設計しています。
マークシートは読み取り機に合わせた設計が必要で、0.0001ミリ単位の正確な作業が不可欠です。
完成した用紙は品質のチェック・実機による読み取りも行います。
例えば、文字のバランスや記入のしやすさ・誤字脱字などの確認。
デザインの乱れや使いやすさも一つずつチェックしていきます。
品質にチェックを行ったあとは、実際に読み取りの検証。
これは重要な作業で、せっかく納品されたマークシートが使用できないなどのトラブルを防止するためには欠かせないことなのです。
このように、ひとつずつデザインや使い心地・読み取り府不良がないかなどをしっかり確認していきます。
マークシートの色はどんなものがあって、カスタマイズはできますか?
マークシートは通常、黒とドロップアウトカラーの2色印刷となっています。
ドロップアウトカラーとは、罫線に使用する色でOMR(機械の読み取りセンサー)に反応しない色で、マニュアルで色の指定がされています。
つまり、黒と複数あるドロップアウトカラーの中から好きな色を選ぶことが可能。
赤や青・オレンジといったようにバリエーションも多くあるので、用途にあった組み合わせができます。
例えば、「試験科目によってマークシートの色を変更したい」「はっきりとした見やすい色にしたい」など希望に合わせたカスタマイズが可能なのです。
マークシートのサイズはどれくらいですか?
一般的なサイズはA4サイズですが、大きさを選ぶこともできます。
最も小さいJISサイズから、A4よりも大きいサイズまで。
入試などはB5サイズ、資格試験はA4サイズのものが多いです。
どのような使い方をするのかによって適切な大きさを判断するといいですね。
ただし、注文先によってサイズの取り扱いが違うので確認が必要です。
イラストや写真を入れてカスタマイズできますか?
イラストや写真を入れたカスタマイズも可能です。
自社の使用目的に適したマークシートの作成ができて、わかりやすくすることも。
例えば、地図や機械などのイラストを挿入すれば、直接該当部位をマークすることもできます。
このように、解答者に対して答えやすい用紙を作成できるのも魅力のひとつです。
マークする部分の形は選べますか?
マークの種類も目的に合わせて選ぶことができます。
マークする部分の形は様々な種類があり、楕円・正円型・四角型・カッコ型など。
楕円は力学上、「0」の動きが反復しやすいといった研究結果から、最も塗りつぶしやすい形と言われています。
正円型は楕円よりもマークの幅が広く、等間隔でマークを並べた場合に余白が広くなることが特徴です。
四角形やカッコ型は塗りつぶしの範囲が狭いことが特徴で、マークを等間隔で並べた場合に余白を広くとることができます。
設問数は1枚のマークシートにどれくらい入りますか?
A4サイズ・JISカードサイズに受験番号や氏名などを記載した場合、それぞれ選択肢と設問数がどれくらい入るかについてお答えします。
A4サイズ(片面・横位置)の場合
A4サイズの場合、選択肢が5つの場合は150問程度・選択肢10つの場合は100問程度の設問が入ります。
設問数も多く、7ケタの受験番号が記入できるため、様々なテストに対応が可能です。
JISカードサイズ(片面・横位置)の場合
JISカードサイズの場合、選択肢が5つの場合は100問程度・選択肢10つの場合は50問程度の設問が入ります。
中学や高校ではこのサイズがよく利用されており、小テストなどに適しています。
マークシートに最適な設問数はどれくらいですか?
試験にマークシートを使用する場合、設問数が多くても少なくてもいけません
仮に60分で試験時間の設定をした場合、35問程度が適量と言われています。
これは大学入試センター試験の回答時間と出題数から計算した数字です。
計算の必要がある問題のときは1問あたりおよそ2分かかり、一方計算の必要がないときはおよそ1.5分かかるといった結果がでています。
この結果から、1問1分という考えがちな単純計算ではない、35問が負荷のない出題数とされているのです。
設問数が少ないときはどうなりますか?
選択肢や設問数が少ない場合は、空いたスペースなどに自社の希望するロゴ・イラストなどを入れることができます。
こうすることで、マークとマークの間隔を広くとるレイアウトが可能です。
マーク間が広くなると、視認性が増すので塗りやすくなるといったメリットもあります。
マークするにあたって最適な筆記用具はなんですか?
マークするにあたって最適な筆記用具は、HB・Bの鉛筆が推奨されています。
通常のOMRは、鉛筆以外で塗ったボールペンなどのマーク部分はデータ化できません。
これは、OMRがマークシートを読み取る際、センサが鉛筆に含まれるカーボンに反応しているためです。
さらに、マークシートに光をあて、カーボンの反射を読み取ってマークの有無を認識します。
このようなことから、太く塗りやすく・芯が柔らかいHB、Bの鉛筆を使うことがもっとも良いとしているのです。
OMRは、鉛筆の消し残しがあってもマーク濃度を16段階で検出することができるので、誤反応してしまうことはまずありません。
ボールペンなどは使えますか?
OMRの可視光センサで対応すれば使えます。
可視光センサの光は、ボールペンでも認識することが可能です。
例えば、記入者の筆記用具を限定できない場合などもマークシートが使えます。
一般的なOMRは、ボールペンの使用はできません。
もし、記入してしまったマークシートがあった場合、鉛筆で塗り直す必要があります。
ただし、可視光センサの場合、マークシートの刷り色は赤やオレンジなどの暖色系に限定されます。
処理速度や必要な保管スペースも教えてください!
OMRの処理速度は1000枚程度のマークシートを30分から1時間で処理することが可能。
これはかなり速いほうで、0.01%以下の誤認識率という高精度での電子データ化はOMR機器以外の実現は不可能と言われています。
1000枚程度なら、長さ310mm×高さ221mm程度の段ボールに入れることができるのでスペースも多く取りません。
実際にマークシートの導入をすると費用はどれくらいですか?
実際にマークシートの導入にかかる費用は取り扱いの会社によって様々ですが、おおよその目安は初回10万円程度です。
OMRの導入まで検討すると100万円程度になることもあります。
マークシート用紙・OMR・読み取りソフトが必要ですし、見積もりや特徴を把握して自社の利用目的などに合わせた選択をしなくてはいけません。
マークシートの無料版ってあるの?
無料のマークシートがあるのをご存じでしょうか?企業によっては無料でマークシートを提供してくれているところもあります。
下記ページでは無料版のマークシート用紙・ソフトを取り扱っている会社を調査しました。有料版マークシート用紙・ソフトと無料版の違い、コスパの良いマークシート読み取り機(スキャナ)に関する情報などもまとめています。
無料版マークシートに興味がある方は参考にしてみてください。
記述式にも対応できる
おすすめのマークシート会社2選
スキャネット

引用元:スキャネット公式HP
(http://www.scanet.jp/)
- 集計/採点用ソフトの費用
- 無料ソフトあり※有料ソフト99,000円~
- 取り扱っている
読み取り機の種類
- スキャナ44,000円~
- 導入にかかる最低費用
- 48,180円
教育ソフトウェア

引用元:教育ソフトウェア公式HP
(http://www.kyoikusw.co.jp/)
- 集計/採点用ソフトの費用
- 107,800円~
- 取り扱っている
読み取り機の種類
- OMR※費用は要問合せ
- 導入にかかる最低費用
- 622,600円
【調査対象】
2023/5/8時点、Google検索で「マークシート 導入」と調べ、検索結果に表示された上位50社を選出。
【選定基準】
その中でマークシート、集計/採点用ソフト、読み取り機の金額が明記されている2社をピックアップ。