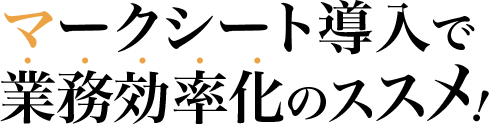公開日:
|更新日:
ストレスチェックの分析方法・集団分析とは
ストレスチェックの集団分析は、組織改善に役立つ分析方法です。実施に当たって気を付けたいことやメリット、チェック結果の分析方法について解説します。
ストレスチェックの集団分析とは
集団分析の目的と意義
集団分析は、組織全体のストレス状況を把握し、職場環境の質を向上させるための重要なステップです。ストレスチェックの結果を個人単位ではなく部署やチーム、職種などの集団ごとに集計・分析することで、職場のどこにストレスの高まりがあるのか、どのような傾向があるのかを把握できます。これにより、個人の悩みに留まらず、組織としての課題を可視化し、より効果的な職場改善の一歩を踏み出せるようになります。
また、集団分析は従業員一人ひとりのプライバシーを守りながら、職場全体の状態を把握できる手法です。個人が特定されることなくデータが集計されるため、従業員も安心してストレスチェックに参加しやすくなります。分析の結果は、組織の健全な発展や働く人々の健康づくりに直結するため、現代の職場には欠かせない取り組みだと言えるでしょう。
集団分析の基本的な手法
集団分析では、まず対象となる集団(例:部署・チーム・職種・年齢層など)を明確に設定し、それぞれのグループごとにストレスチェックの結果を集計します。たとえば、同じ会社内でも営業部と事務部、若手とベテランなど、グループごとの特徴やストレス要因を比較することで、組織内の多様な傾向を明らかにできます。
その後、集計データを分析する際には平均値や分布、特定項目の割合などを見ながら、どの集団にどのようなストレス要因が強く表れているかを客観的に評価します。分析結果はグラフや表にまとめると、視覚的にもわかりやすく、現場での共有や改善策の立案にも役立ちます。
集団分析を行うメリット
職場環境の課題を可視化
集団分析を行うことで、組織や部署ごとにどのようなストレス要因が存在しているのかが明確になります。たとえば「残業時間が長い」「コミュニケーションが少ない」「業務量の偏りがある」など、ストレスの原因を具体的に特定できるため、組織改善の方向性が見えてきます。これにより、漠然とした不安や不満ではなく、根本的な課題へのアプローチがしやすくなります。
さらに、数値や傾向を客観的に把握できることで、改善の優先順位も明確に設定できます。現場の声だけに頼るのではなく、実際のデータをもとに判断できる点は、組織改革を進めるうえで大きなメリットです。客観性と具体性を備えた課題発見は、実効性の高い施策づくりにつながります。
メンタルヘルス不調の予防
集団分析によって、ストレスの高い集団や部署を早期に発見できるため、メンタルヘルス不調の予防につなげることができます。従業員の心身の健康に異変が生じる前に、組織としてサポート体制を強化したり、業務改善を図ることが可能となります。これは、離職率の低下や職場の安心感の向上にも効果的です。
また、従業員自身も「自分たちの声がデータとして反映されている」と感じることで、会社への信頼感が高まります。管理職や人事担当者にとっても、具体的なデータがあることで社内提案や改善活動がスムーズに進めやすくなります。メンタルヘルス対策を積極的に行う土台づくりとして、集団分析は非常に有効です。
組織全体の生産性向上
職場環境の改善は、従業員一人ひとりの働きやすさを高め、結果的に組織全体の生産性向上にもつながります。集団分析を通じて業務量の調整や人員配置の見直し、コミュニケーションの強化など具体的な取り組みが行えるため、働きやすい環境を作る一助となります。
また、ストレスの要因が減り、従業員の満足度が高まることで、モチベーションやエンゲージメントも向上します。こうした良い循環が生まれることで、組織全体としての成長や成果がさらに高まりやすくなるのです。職場改善は単なる福利厚生の一環ではなく、経営に直結する重要な戦略の一つです。
集団分析の作成方法
分析対象の集団を明確にする
集団分析の第一歩は、「どのような集団を分析対象とするか」を明確に決めることです。部署、チーム、職種、年齢層など、分析の目的や現場の実態に合わせてグループ分けを行いましょう。たとえば、営業部だけでなく、営業拠点ごと、年代ごとに分けることで、より細かな傾向や課題を発見しやすくなります。
こうした集団設定は、課題の発見だけでなく、今後の改善策を講じる際の具体的なターゲット設定にも役立ちます。集団ごとの特徴を意識した分析は、実際の現場での効果的な施策立案のカギとなります。
データの収集と整理
ストレスチェックの結果を正確に分析するためには、まず集団ごとに必要なデータを正確に集計し、分析しやすい形式に整理することが大切です。紙ベースやデジタルツールなど、自社の運用に合った方法で、回答内容をもれなく集計しましょう。
データ整理の段階で大切なのは、集団ごとにデータの偏りや抜けがないかをチェックすることです。また、集計方法や評価基準をあらかじめ統一しておくことで、分析結果の信頼性も高まります。データの正確性は、良い分析の基盤です。
分析手法の選定
集計したデータをどう分析するかも重要なポイントです。平均値や中央値、分布の幅などの基本統計量の比較や、ストレス要因ごとの傾向分析など、目的に合わせた手法を選びましょう。例えば、部署間の平均スコアの差や、特定のストレス要因の多い集団の抽出などが考えられます。
分析手法を選ぶ際には、専門知識が必要になる場合もあります。社内だけで難しいと感じたら、外部の専門家に相談するのも選択肢のひとつです。適切な手法で分析を行うことで、より実態に即した課題発見につながります。
集団分析の結果の分析方法
経年比較による変化の把握
ストレスチェックを毎年継続的に実施し、過去のデータと現在のデータを比較することで、職場のストレス状況がどう変化しているかを把握できます。経年比較は、取り組みの成果や改善の効果を評価するうえでとても重要な指標です。「去年はストレス度が高かった部署が、今年は改善している」など、変化の有無や方向性を見極める材料となります。
経年比較の結果は、さらなる施策の立案や目標設定にも役立ちます。良い変化が見られればモチベーションアップに、逆に改善が見られない場合は課題の掘り下げや対策強化につなげましょう。データの積み重ねが組織の成長を後押しします。
部署間・職種間の比較
異なる部署や職種、拠点ごとのデータを比較することで、どの集団にどんな課題があるのかを具体的に把握できます。たとえば、同じ企業内でも部署ごとにストレスの感じ方や要因が大きく異なる場合があります。部署間で傾向がはっきり出る場合は、業務内容や職場環境に原因が隠れていることも。
また、職種や年代ごとに比較することで、組織内の多様性や特有の課題も明らかになります。課題が集中している部署や集団には、重点的なフォローや改善策の実施が求められます。細かな比較分析を通じて、より実効性の高い改善が可能になります。
仕事のストレス判定図の見方
量-コントロール判定図の解釈
量-コントロール判定図は、従業員が感じている仕事の「量」と「コントロール度(裁量)」のバランスを可視化する図です。業務量が多すぎる、もしくは仕事の進め方に自分の意見が反映されにくい(コントロール度が低い)といった場合、ストレスが高まる傾向が見られます。この図を見ることで、どの部署やグループで「業務過多」や「裁量権の不足」が課題となっているのかを明確にできます。
グラフや分布で結果を把握しやすく、現場での具体的な業務改善につなげやすい点も大きな特徴です。例えば「この部署は業務量が多い一方でコントロール度が低い」という結果が出た場合は、業務配分の見直しやマネジメントの仕方を考えるきっかけになります。
職場の支援判定図の活用
職場の支援判定図は、従業員がどれだけ上司や同僚からサポートを感じているかを測る指標です。職場での支援が充実しているとストレスが軽減される傾向があり、逆にサポートが乏しい環境では孤独感やストレスが増大しやすくなります。支援判定図の分析結果からは、コミュニケーションやチームワークの強化が必要な部署や集団を特定することができます。
分析結果は、職場全体の風土づくりや人間関係の改善にも活用できます。支援の強化策として、上司の面談頻度を増やしたり、チームでの交流機会を増やすなど、組織の現状に即した具体的な取り組みに繋げることができます。
業務を妨げないマークシートでストレスチェックを最適化
効率的な実施方法の導入
ストレスチェックの運用で大切なのは、従業員の負担を最小限に抑えることです。マークシート方式の導入は、その一つの有効な手段です。紙やWeb上でのマークシートは、操作が簡単で受検者も回答しやすく、業務を妨げることなくストレスチェックを実施できます。
また、マークシートは集計・分析も効率的に行えるため、担当者の作業負担軽減にもつながります。多忙な現場でも円滑にストレスチェックを運用できるよう、効率化を意識した実施方法の選定が重要です。
データの迅速な分析と活用
効率的な実施方法により得られたデータは、速やかに分析・フィードバックを行うことで、組織改善に直結します。分析結果が迅速に現場に届けば、タイムリーに対策を講じることができ、従業員も変化を実感しやすくなります。
また、ストレスチェックを単なる年中行事に終わらせるのではなく、分析結果を現場にしっかり還元し、実際の改善活動に活用することが大切です。集団分析のサイクルを円滑に回すことで、組織全体の健康度や働きやすさを着実に高めていくことができます。
記述式にも対応できる
おすすめのマークシート会社2選
スキャネット

引用元:スキャネット公式HP
(http://www.scanet.jp/)
- 集計/採点用ソフトの費用
- 無料ソフトあり※有料ソフト99,000円~
- 取り扱っている
読み取り機の種類
- スキャナ44,000円~
- 導入にかかる最低費用
- 48,180円
教育ソフトウェア

引用元:教育ソフトウェア公式HP
(http://www.kyoikusw.co.jp/)
- 集計/採点用ソフトの費用
- 107,800円~
- 取り扱っている
読み取り機の種類
- OMR※費用は要問合せ
- 導入にかかる最低費用
- 622,600円
【調査対象】
2023/5/8時点、Google検索で「マークシート 導入」と調べ、検索結果に表示された上位50社を選出。
【選定基準】
その中でマークシート、集計/採点用ソフト、読み取り機の金額が明記されている2社をピックアップ。