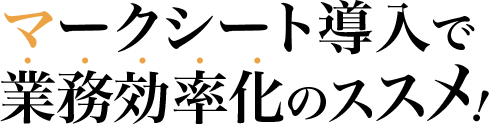公開日:
|更新日:
マークシートを使ったアンケート分析にコレスポンデンス分析を活用
アンケート分析手法「コレスポンデンス分析」について
アンケートを集計した結果を表にまとめる際、複数の設問項目の集計結果を一つの票としてまとめたものを「クロス集計表」と呼びます。クロス集計表であれば一つの表で「どの質問に・何人がどう答えたのか」を確認することができますが、項目が多ければ多いほど表を見づらくなり、混乱してしまいます。膨大な数の集計結果を一目で見やすくするために考案された方法が「コレスポンデンス分析」と言います。略して「コレポン」と呼ばれることも。
コレスポンデンス分析を行う際は、十字にクロスするマップを作り、そこに散布図として集計結果を並べていく方法を取ります。例えば「コスト」「デザイン」の二項目をコレスポンデンス分析する場合、「コストが高いがデザインも良い商品A」との結果が出た場合、縦軸コストで横軸デザインなら右上の方に商品Aが位置します。それと対極の「コストが低いがデザインが悪い商品B」は左下に位置するわけです。
パッと見ただけで複数項目の位置を見ることができるため、多くの物を同時に比較したり評価したりといった場合に活躍する分析方法です。クロス集計表の項目が多すぎてごちゃごちゃと見づらい場合や、それぞれの項目の立場や関係を一目で確認したいとき、コレスポンデンス分析が採用されています。
「コレスポンデンス分析」をアンケート分析で使うには
コレスポンデンス分析はアンケートの分析・調査でもよく活用されている方法です。アンケート分析で行う場合、まずは集計結果をクロス集計表にまとめるところから始めます。アンケートから得た集計データをクロス集計して、それぞれの項目ごとに数値化しておきます。例えば商品A~Eまでの5つを、「コスト・センス・機能性・知名度・耐久性」の5項目別に評価し、数値化して集計表にまとめます。
まとめた集計表を使って散布図として表示すれば、コレスポンデンス分析の完了です。ここで重要なのは、縦軸と横軸の決め方です。前述の例でいくと、「センス・機能性・耐久性」を縦軸「品質」として、「コスト・知名度」を横軸「親しみやすさ」として位置するという解釈の方法があります。ここで縦軸と横軸の決め手となるのは、分析する人の解釈です。
大切なのは一目で複数の項目を把握し、位置関係をチェックできること。分析結果を見比べれば今後の課題が見つかったり、逆に他社や競合との関係を把握したりといった分析に活用できます。
「コレスポンデンス分析」をアンケート分析で使うために知っておきたい知識
コレスポンデンス分析は様々なクロス集計表の分析方法として活用できます。アンケート分析としてはもちろんですが、他にも採点結果の集計などにも活用できる方法です。他社との比較や自社の課題の発見、今後のターゲットへのアプローチ方法など…さまざまな目的で利用できます。
コレスポンデンス分析をするのであれば、まずどんな情報を得たいのかをハッキリ決めておきましょう。アンケート回答者からのイメージの良し悪しを比較したいのか、それとも回答者層ごとに持っているイメージの違いを比較したいのか…。コレスポンデンス分析を使って分析できる情報はたくさんあります。
また、コレスポンデンス分析は俯瞰的な視点から数ある情報を整理したい場合にこそ活用できる分析方法です。表の状態やグラフの状態だと上手く見比べられない情報たちを平面マップの上で分かりやすく位置づけることができます。この特性を理解して適切に活用できるようになることが、コレスポンデンス分析を上手く使いこなすポイントです。
「コレスポンデンス分析」をアンケート分析で使う場合に注意したいこと
アンケートを実施して集計した場合、様々な数値が明確化するでしょう。「この質問に何%がどう答えた」という情報が明確化されているのが、クロス集計表の特徴です。これに対してコレスポンデンス分析をした場合は、ただの位置づけしか情報が得られません。
例えば縦軸が「品質」で横軸が「親しみやすさ」だった場合、右上に位置する商品Aがあったとしても、一体何人が商品Aに対して「機能性が高い」などと回答したのか、その数値は分からないのです。あくまで大まかなマップとして散布図をつくるだけですから、詳細な数値を知りたい場合はコレスポンデンス分析が向いていません。縦軸と横軸の2つがあるマップの上に、1つの点として表示されるだけです。
また、コレスポンデンス分析を行う人の解釈によって微妙にできる図表が変化するのも、コレスポンデンス分析の注意点の一つ。縦軸と横軸をどう設定するかによって、知りたい情報と微妙に食い違った散布図が出来てしまうこともあります。
「コレスポンデンス分析」をアンケート分析で使う上でのまとめ
コレスポンデンス分析は汎用性が非常に高く、アンケート分析をその後に活かすために有用な手法です。一目で項目を比較して位置関係を把握できることにより、それまで見えてこなかった新たな課題や強みに気づくこともあるでしょう。
ただしコレスポンデンス分析ならではの特徴や強みを理解していないと、上手くその便利さを活かせません。分析を何に役立てるのか、目的をハッキリ決めてから分析を行いましょう。
マークシートの無料版ってあるの?
無料のマークシートがあるのをご存じでしょうか?企業によっては無料でマークシートを提供してくれているところもあります。
下記ページでは無料版のマークシート用紙・ソフトを取り扱っている会社を調査しました。有料版マークシート用紙・ソフトと無料版の違い、コスパの良いマークシート読み取り機(スキャナ)に関する情報などもまとめています。
無料版マークシートに興味がある方は参考にしてみてください。
記述式にも対応できる
おすすめのマークシート会社2選
スキャネット

引用元:スキャネット公式HP
(http://www.scanet.jp/)
- 集計/採点用ソフトの費用
- 無料ソフトあり※有料ソフト99,000円~
- 取り扱っている
読み取り機の種類
- スキャナ44,000円~
- 導入にかかる最低費用
- 48,180円
教育ソフトウェア

引用元:教育ソフトウェア公式HP
(http://www.kyoikusw.co.jp/)
- 集計/採点用ソフトの費用
- 107,800円~
- 取り扱っている
読み取り機の種類
- OMR※費用は要問合せ
- 導入にかかる最低費用
- 622,600円
【調査対象】
2023/5/8時点、Google検索で「マークシート 導入」と調べ、検索結果に表示された上位50社を選出。
【選定基準】
その中でマークシート、集計/採点用ソフト、読み取り機の金額が明記されている2社をピックアップ。