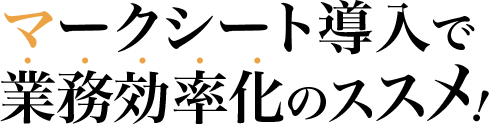公開日:
|更新日:
ストレスチェックの義務化
こちらのページでは、ストレスチェック制度の義務化に関する概要をはじめ、制度設計の背景や事業者に求められる行動などについてまとめています。
ストレスチェックとは
まずストレスチェックとはどのような制度なのか、概要と特徴を解説します。
ストレスチェック制度は労働者のメンタルヘルス確認
厚生労働省で定めた労働者のメンタルヘルスの一次予防や二次予防へつなげるための検査のことを、ストレスチェック制度と言います。
一般的な健康診断とは異なり、検査項目が記載された書類に現在の状況やストレス具合などを詳細に記載するのが特徴です。医師や保健師が各労働者から提出された検査書類をチェックし、メンタルヘルスの不調やストレスの状態などを判断していきます。
なお、ストレスチェックの義務化に該当する企業は従業員50名以上の事業規模と定められていて、50名未満の企業については努力義務です。
ストレスチェックの実施者は医師や保健師など
ストレスチェックに従事するためには、条件に合致する実施者がストレスチェックの準備および検査の実施を行わなければいけません。
具体的には法律で定められた医師や保健師、看護師、歯科医師、公認心理士といった特定の資格取得者に限られています。そのため、自社に産業医を排していない場合は、外部機関への委託が必要です。
ストレスチェックの主な流れ
まずは事業者がストレスチェック前に、従業員へ実施時期や内容を説明します。実施日には実施者として認められている医師や保健師などがストレスチェックを行い、各情報から高ストレスや低ストレス状態など分析していくという流れです。
高ストレス状態やメンタルヘルスに不調がある従業員については、従業員の希望により医師との面談や診察を行ってもらうなど対策を講じます。
ストレスチェックの義務化
続いては、ストレスチェックの義務化に関する概要と、義務化へ至った背景などについて解説していきます。
2014年に法律改正したことでストレスチェックが義務化となる
ストレスチェック制度は、2014年6月に公布され2015年に義務付けられた法律です。内容は50名以上の企業でのストレスチェック義務化、そして医師による面接指導や就業上の措置(労働時間の短縮や業務内容の見直し)を施し、従業員のメンタルヘルス不調をチェックしたり改善したりすることが必要となりました。
日本は精神障害の労災認定が増加している
ストレスチェックが義務化された背景には、日本が抱える労災に関する問題も関係しています。その問題は、平成23年度の精神障害の労災請求件数が3年連続(平成21~23年度)で過去最高を更新している点です。
(PDF)参照元:厚生労働省「表2-1 精神障害の労災補償状況」
精神障害の労災請求が増えているということは、少なからず職場環境や業務内容、組織内に問題を抱えているといえます。健康問題や自殺にもつながる重大な問題です。業務効率の低下や退職や休職などによる人材不足のリスクもあり、早急に労働者の健康チェックや改善が必要となっています。
そこで厚生労働省は、労働者のメンタルケアを目的としたストレスチェック制度を法律で定めました。
ストレスチェックはメンタルヘルスケア不調の一次予防(医師による助言や診断)や職場環境の見直しによる二次予防だけでなく、職場復帰などの三次予防を含めた労働者のメンタルケアに関する環境整備を求めています。事業者は、ストレスチェックの準備だけでなく、二次予防に該当する職場環境や労働時間、各部署の組織改革などにも着手しなければなりません。
ストレスチェックの実施期限について
厚生労働省のマニュアルでは、ストレスチェックの実施頻度は前回の実施日から1年以内と定められています。実施頻度について1年に1回と決められているわけではなく、半年に1回のペースで実施しても問題ありません。正確性を重視する場合、ストレスチェックの実施は以前チェックを行った時と同じ時期に行うのがおすすめです。
閑散期・繁忙期のストレスチェックは適切か?
労働者の採用時期が一定でない事業場では、入社時期とストレスチェックの実施時期が重なることがあります。ストレスチェックは労働者の体調やメンタルヘルスを把握するために実施するもの。同じ調査内容でも閑散期と繁忙期では、対象者のコンディションによって結果に差が出る可能性もあります。この場合は閑散期と繁忙期の両方でストレスチェックを受けられるように、短いスパンでストレスチェックを実施しましょう。繁忙期にストレスチェックを実施すれば、従業員が感じるストレスの上限を把握できます。しかし繁忙期に行うと人手不足になり、仕事が回らなくなることが問題です。ストレスチェックと業務が両立できるように調整する必要があります。
ストレスチェックの目的は従業員の心身の健康管理を行い、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことです。従業員が体調やメンタルに気を使いにくい時期を避けて、ストレスチェックを実施するのが望ましいでしょう。
ストレスチェックの未実施率(※)
2015年12月1日に義務化されたストレスチェック。2017年7月に厚生労働省がストレスチェックの実施状況を調査し公表しました。ストレスチェックの実施報告書の提出があった事業場の割合は82.9%。1割以上の事業場がストレスチェックの報告書を提出していないことが分かります。提出状況を事業場の規模別にみると、50~99人の事業場が78.9%、100~299人が86.0%、300~999人が93.0%、1,000人以上が99.5%。大規模の事業場よりも小規模の事業場のほうが、ストレスチェックの報告書を提出していない割合が高いことが分かりました。
ストレスチェックを前回実施日から1年以内に実施しなかった場合は、労働基準監督署から注意・勧告を受けることも。通知が届いた際は実施ができなかった理由を説明し、早くストレスチェックを実施・報告してください。
(PDF)参照元:厚生労働省「ストレスチェック制度の実施状況」
ストレスチェック未実施の罰則金について
ストレスチェックは、実施した後に労働基準監督署に報告する義務があります。報告を怠り、労働基準監督署からの勧告を無視すると、罰則を受けなければなりません。
ストレスチェック実施の義務化に伴い、以下3つのいずれかを満たす者には50万円以下の罰則金が科せられます。
参照元:労働安全衛生法/第120条第5項
- ストレスチェックの実施後に労働基準監督署に報告をしていない
- ストレスチェックの結果について虚偽の報告をした
- ストレスチェックを実施しておらず勧告を受けた後も労働基準監督署に出頭せず、ストレスチェックを実施しない
ストレスチェックの未報告・未実施が発覚後、すぐに罰則が科せられるわけではありません。まず労働基準監督署から対象者に勧告通知が送付されます。その後、勧告を無視して、ストレスチェックを実施しない場合に、50万円以下の罰則金が科せられます。期限内にストレスチェックを実施するようにし、その後はできるだけ早く労働基準監督署に報告しましょう。
安全配慮義務違反になる可能性について
ストレスチェック未実装によるペナルティは、罰則金の支払いだけではありません。チェックを実施しないことで、安全配慮義務違反になる可能性があることも念頭に入れておいてください。
安全配慮義務とは、事業場が労働者の命や安全に対して配慮しなければいけないと定めた義務のことです。安全配慮義務を果たすためには、従業員が安全に働けるような環境を考え、対策を立てる必要があります.
対策を考える際の軸となるのは「作業環境」と「健康管理」の2つ。労働者の「健康管理」を事業場が適切に行うための手段の一つがストレスチェックの実施です。安全配慮義務に違反すると、多額の損害賠償請求を受ける可能性も…。事業所の評判低下にも繋がることもあるので注意しましょう。
ストレスチェックの実施は労働者に対する安全配慮義務を守ることにも繋がります。どちらも事業場として守らなければいけない義務なので、注意しておきましょう。
ストレスチェックの実施義務の有無
ストレスチェックの実施はすべての事業場に対して義務付けられているわけではありません。実施義務の有無は事業場で働く従業員の人数によって決まります。それぞれの事業場の特徴について確認して、法令に沿った運営を行いましょう。
ストレスチェックの実施義務がある事業場
ストレスチェックの実施義務があるのは、50人以上の労働者が働く事業場です。
事業場とは、企業全体ではなく、支社や営業所、工場のように、独立して業務が行われている場所のことを指します。また実施義務は民間企業だけでなく、学校職員や公的医療機関などの公務員も対象です。
労働者数を判断する基準は、対象者が常態として働いているかどうかです。例えば週1回の勤務であっても継続して雇用している労働者はストレスチェック実施の対象者となります。正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマー、派遣社員への実施も必要です。
ストレスチェックの実施義務がない事業場
ストレスチェックの実施義務がないのは、労働者の人数が50人未満の事業場です。
50人未満の事業場の場合、ストレスチェックの実施は義務ではなく努力義務となります。このためストレスチェックを実施しなくても、実施義務のある事業場のように罰則を受ける必要はありません。
働き方改革が進むにつれて、労働者の安全と健康を管理することが重要視されています。実施義務のない事業場であっても、ストレスチェックの実施は運営するにあたってメリットに。積極的に実施をしていきましょう。50人未満の事業場がストレスチェックを行う場合も、厚生労働省のマニュアルに従って行います。ただし労働基準監督署への報告は義務付けられていません。
年々増え続けるメンタルヘルス不調者、国は労働者がメンタルヘルスに不調を抱えることを未然に防ぐことを目的とした制度を設けています。事業場がストレスチェックを取り入れやすいように、50人未満の事業場に対して、厚生労働省はストレスチェック助成金を用意しています。実施の際は、厚生労働省からの助成金を活用しましょう。
ストレスチェックの実施義務がなくても実施が推奨されるケース
チェックの実施義務がない場合でも、ストレスチェックを行うことを推奨されるケースもあります。実施により、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防げる可能性がアップ。事業場でのストレス要因を明らかにすることで、心身の健康状態を保つことができ、労働者の生産性を高めることにも繋がります。手間や費用がかかりますが、より良い環境の事業場を目指すためにストレスチェックを実施した方が良いでしょう。実施が推奨されるケースを3つ紹介します。
本社がストレスチェックを実施している
実施義務がない50人未満の事業場でも、本社や別の支店がストレスチェックを実施している場合は、ストレスチェックを行うことを推奨します。
本社や別の支店が毎年ストレスチェックを実施しているのであれば、チェックするためのノウハウは社内にあるはず。
まずは本社のストレスチェック制度に詳しい社員に相談してください。ストレスチェックを実施できる環境を利用して、労働者の健康管理の質を高めましょう。
従業員がメンタルヘルスに不調を抱えている
50人未満の事業場であっても、現在メンタルヘルスに不調を抱える労働者がいる場合には、ストレスチェックの実施が推奨されます。
また今は問題がなくても、過去にメンタルヘルス不調者がいた事業場もストレスチェックを実施する必要があります。なぜなら事業場に大きなストレス要因が改善しないまま残っている可能性があるからです。
労働契約法により、事業場は従業員が安全で健康に労働できるよう配慮することが義務付けられています。ストレスチェックの実施で労働者に対して心身の健康管理を行い、新たなメンタルヘルス不調者を出さないことも重要です。
業務負荷の高い仕事をしている
ストレスチェックの実施を推奨するケースとして、業務負荷の高い仕事をしている事業場であることが挙げられます。
業務負荷が高いとされるのは長時間の労働を行っていたり、小さなミスが大きな怪我につながる恐れがあったりする事業場です。事業場の管理者が労働者の健康面に十分な配慮をしていても、労働者は業務上のストレスについて管理者に直接相談することは難しいでしょう。
ストレスチェックを実施することで、管理者に直接相談しづらい業務上のストレスを目視化できます。事業場の労働者が感じるストレスのレベルを把握し、対策を立てるための判断材料として管理者が活用。大きなストレスを抱える労働者が見つかった場合には、適切な対応とケアをすることが大切です。
まとめ
ストレスチェックの義務化は、社会問題とも捉えられる精神障害の労災請求・認定件数の増加が関係しています。
より良い職場環境を作るためにも、ストレスチェックの構築や導入に時間がかかっている事業者はストレスチェックツールを検討してみてはいかがでしょうか。
チェックツールを提供しているサービスでは、マークシートや読み取り機器を用いて集計作業を効率的に進めてくれます。さらに料金は、1,000人あたり10万円未満のケースもあり、負担を抑えながら利用できるのがメリットです。
まずはチェックツールのコストやプラン内容を確認し、自社の予算や従業員数に合ったサービスから比較検討してみてください。
記述式にも対応できる
おすすめのマークシート会社2選
スキャネット

引用元:スキャネット公式HP
(http://www.scanet.jp/)
- 集計/採点用ソフトの費用
- 無料ソフトあり※有料ソフト99,000円~
- 取り扱っている
読み取り機の種類
- スキャナ44,000円~
- 導入にかかる最低費用
- 48,180円
教育ソフトウェア

引用元:教育ソフトウェア公式HP
(http://www.kyoikusw.co.jp/)
- 集計/採点用ソフトの費用
- 107,800円~
- 取り扱っている
読み取り機の種類
- OMR※費用は要問合せ
- 導入にかかる最低費用
- 622,600円
【調査対象】
2023/5/8時点、Google検索で「マークシート 導入」と調べ、検索結果に表示された上位50社を選出。
【選定基準】
その中でマークシート、集計/採点用ソフト、読み取り機の金額が明記されている2社をピックアップ。